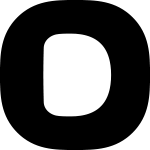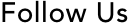【magazine】武蔵野美術大学公開講座2019 第4回レポート 「人類の身体と道具と社会のデザイン」を学ぶ!
さまざまな分野の創造的リーダーに話を伺ってきた、武蔵野美術大学とWEデザインスクールの共同開催による社会人向け公開講座。探検家で人類学者の関野吉晴さんを迎えたその第四回「『人類の身体と道具と社会のデザイン』を学ぶ!」が、10月17日、東京ミッドタウンのインターナショナル・デザイン・リエゾンセンターで行われた。人類の歩みを辿る5万キロの旅「グレートジャーニー」で知られ、ムサビでも長年教鞭を執ってきた関野さん。講座のモデレーターを務めるOFFICE HALO代表/WEデザインスクール主宰の稲葉裕美さんを聞き手に、旅や教育を通じて探究してきた根源的な思考を語った。
文=杉原環樹(ライター)
■ 人類のルーツをめぐる、普遍的な問い
関野さんが長年担当してきた「文化人類学」は、ムサビでも屈指の人気授業だ。身体を通して世界と接してきた経験から来るその言葉や知恵は、アートやデザインなど、普段は現代という時代に立脚してものづくりを行う学生の思考や常識を揺さぶってきた。今回の講座で聞き手を務めている稲葉さんも、ムサビ時代にその薫陶を受けた一人。「関野さんの授業では、自分の芯が見えてくる感覚があった。その感覚を、ぜひ参加者のみなさんにも体験してもらいたい」と話す。
1949年生まれの関野さんは、一橋大学に入学後、探検部を創設。当時から半世紀にわたり続けているアマゾンへの旅は、関野さんのライフワークだ。日本とは異なる現地の社会慣習や時間感覚に刺激を受け、旅を一生続けるにはどうすればいいかを考えた。研究者や写真家、ジャーナリストなどの選択肢もあるなか、関野さんがユニークなのは、そこで医師の道を選んだことだ。
あらためて入学した横浜市立大学医学部を、アマゾンに通いながら6年かけて卒業し、外科医として病院に務めた。医師という選択の理由を、「調査や取材のかたちではなく、アマゾンの人たちとは友達でいたかったんです。怪我を治せれば、彼らの役に立つこともできる」と語る。
その後、病院勤めと並行して旅を続けた関野さんは、40代にしてある壮大な計画を思い立つ。アフリカからユーラシア大陸や北米大陸を経て世界に散らばった人類の歩みを、その最終地点である南米の地から遡行する「グレートジャーニー」だ。その動機には、「このアマゾンの人たちは、一体、どのようにしてここに来たのか」という関心があったという。
「ボストン美術館にあるゴッホの絵画に、『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』(1897-98年)というものがあります。ここで示されている問いは、いつの時代の人間も考えてきた普遍的な問いだと思う。それを、真剣に考えようと思ったんです」。
自らに「近代的動力を用いない」というルールを課し、1993年、南米最南端のチリ・ナバリーノ島をカヤックで出発。5万3000キロにおよぶ旅は、足かけ10年の歳月をかけて、2002年に最終目的地であるタンザニアのラエトリに辿り着いた。ゴール間際の地では、「いままでは自分で設けた各地の小さなゴールに早く着きたかったのに、もっと旅を続けたいと初めて思った」という。
会場では、その旅の様子を収めたドキュメンタリー映像も紹介された。
■ 私たちの身体はどのようにデザインされたのか
「『人類の身体と道具と社会のデザイン』を学ぶ!」と題された今回の講座。関野さんは、とりわけそのなかでも「人間の身体のデザインが重要だ。人間の手はキーボードを打つためにデザインされたわけではない」と語り、その形成過程をあらためて振り返った。
たとえば、人類の身体の基礎となる生物が現れたのは、およそ5億年前のカンブリア紀のことだ。この時期には、背骨の原型の脊索を持ち、「人類の祖先」と長年考えられてきたピカイアという海棲生物がいた。動物の身体は、人類のように体内に骨格を持つ「内骨格系」と、昆虫のように皮膚の外に骨格を持つ「外骨格系」に大きく分かれる。現在でも、地球上の総量で重たいのは外骨格系だというが、人類の祖先は内骨格系に属していたために大きくなることができた。
また、関野さんがとくに重視するのは、恐竜の絶滅後、人類の祖先が森で生活を始めた時期の身体の変化だ。当初はネズミのようだったその身体は、木から木に移るため肩を大きく回せるように変化し、鉤爪だった手もモノを握りやすい扁爪になった。また、眼が顔の前面に付いて立体視が可能になり、色彩も認識できるようなった。このように進化とは、「なりたいからなったのではなく、たまたま生存に有利な進化をしたグループが生き残った」のだと関野さんは言う。
さらに関野さんは、人類の進化を辿るなかで、猿の研究者との意見交換も大事にしてきた。というのも猿の世界では、「コミュニティはあるが、家族がいない」からだ。えこ贔屓を許して見返りを求めない「家族」と、贔屓は許さないが貸し借りを求める「コミュニティ」という二つの集団のあり方は、じつは両立することが難しい。「人類は家族だけでは生き延びれないため、その外側にコミュニティを作り、ほかの集団とも連携していった動物なんです」と関野さんは話す。
こうした関野さんの話を受けて、稲葉さんはあらためて学生時代に受講したその授業のインパクトに触れながら、「自分の前提を揺さぶられる感覚。私は高校時代、社会問題への関心から政治家になろうと考えた時期があったが、関野さんの授業を受けて、当時は人間を目の前の現実だけで判断していたと気づいた」と話した。
これに対して関野さんも、「自分がいまここにいることを考えると、いろんなことに感謝しないといけなくなる」と答える。38億年前に最初の命が生まれてから、幾度もの危機を乗り越えた生命の連鎖が現在の世界を作っている。「人は往々にして、先人より自分の方が優れていると思いがち。でも、多くの人はパソコンを使えても、自分で機械は作れない。それは長いものづくりの歴史に支えられていて、人類の歴史も同じ。近過去だけ見ていたら、見えない世界がある」。
■「当たり前のもの」を、その起源から辿ってみる
人類が達成した大きな変化というと、よく取り上げられるのは農業革命や産業革命だ。しかし、先ほどの森での生活の開始や、あるいは森を離れた生活の開始など、それ以前の時代にも振り返るべき重要な変化はある。「現代においてデザインを考えるときにも、そうした長い時間軸での過去現在未来に通じる人間の普遍性を考えないといけないのではないか」と関野さんは問う。
とても興味深かったのが、関野さんがこうした思考を体験するために学生たちと一緒に行ったプロジェクトの数々だ。そのひとつが、2008年から2011年にかけて実施された「縄文号」のプロジェクトである。これは、太古の人類が日本列島にどのようにやってきたのかという関心から、インドネシアから日本までの海を自作の船でエンジンを使わずに航海するという計画だ。
驚くのは、なんと鉄器のための砂鉄集めから始めたというその出発点。収集された砂鉄をたたら製鉄で工具とし、木材も自ら切り出し、インドネシアのスラウェシ島の伝統技術に学びながら半年をかけて造船を行った。総距離4700キロにおよぶ航海は、もちろんGPSもコンパスを使わず、島影と星空だけを頼りに進められた。遅いときは一日で10キロ以下しか進まない。結果、日本の地にたどり着くまでに3年間がかかった。この旅路は、その後、映画にもなった。
乗組員の多くは社会人になる前の卒業生だが、プロジェクトにはムサビ生だけでなく、他大学からも多くの学生が関わっている。その理由を関野さんは、「じつは美大においても、蚕から糸を作るような一からのものづくりは行われていない。そこに若者の欲求があった」と話す。「5キロの工具を作るには、150キロの砂鉄と3トンの松が必要です。つまり、工具の歴史とは森林伐採の歴史でもある。このプロジェクトを通して、そうした視点も学ぶことができる」。
もうひとつ、「カレーライスを一から作る」というプロジェクトも面白い。これは、普段何も考えずに食べている一杯のカレーライスを、米や野菜はもちろんのこと、鶏肉やスパイス、器などから自分たちで作ろうというもの。そのプロセスでは、化学肥料の使用の是非や、愛着が湧いた鶏を殺すべきか否かを巡っての議論も起きた。このプロジェクトも、のちに映画化された。
稲葉さんは、「私たちの普段の生活では、あるものが誰かの手によって生み出されていることは忘れがちだ」と指摘する。これに対して関野さんは、「食べているものは基本的に命。このプロジェクトでは肉屋や魚屋や八百屋以前のことが学べる」と話す。さらに関野さんは、毎年学生を連れて芝浦にある屠場の見学も行っている。誰もが考えることを面倒くさがったり、触れるのが怖くて無意識に避けてしまう物事のなかに、じつは世界を深く知るためのヒントがあるのだ。
■ 大きな挑戦を支えるのは、周囲の「待つ」姿勢
他人には真似できないユニークな活動を行なってきた関野さんだが、その発想は一体どこから来るのだろうか。そう稲葉さんから問われた関野さんは、発想とは、何かをしたり本を読んだりしていると自然に湧いてくるもので、作るものではないと語る。「大事なのは好奇心で、それがないと始まらない。最初に自分がアマゾンを訪れたときも、その土地に身を置くことで自分がどう変化するかに興味があった」。いまも、旅の最後には次の旅の構想が自然に浮かぶという。
また、人が大きな挑戦をするうえでは、周囲の「待つ」態度こそが大切だとも指摘した。グレートジャーニーを計画した30年ほど前、当時のマスコミは、成果が出るかどうかもわからないその構想に気前よく機材を貸してくれたそうだ。「問題は時間を与える側で、待ってくれるなら前衛的な挑戦もできる。それが、現在のように一年で成果を出せと言われてしまうと、大抵の人間は卒なく動いてしまう。でも、そこから本当に感動的なことは生まれないと思います」と話す。
そんな関野さんは、現在、三鷹駅近くのムサビ通信教育課程の施設「三鷹ルーム」で、「地球永住計画」というプロジェクトも展開している。これは、「この奇跡の星(地球)で私たちが生き続けていくためにはどうしたらいいのか」をテーマに活動する取り組みで、関野さんが関心を持つゲストを迎えて月1〜2回ほどのトークを行うなど、独自の学びの場を提供している。
「同時代性と普遍性という二つがあるとすれば、多くの人は同時代性に目を向けて日々を過ごしている。そのなかで、関野さんのお話は私たちに普遍性を問い直す機会をくれる」と稲葉さん。しかし、活動を続けるなかで迷うことはなかったのか? 最後にそう問われると、関野さんは、「つねに迷っています。大学で探検部の部員募集の張り紙をしているときも、将来はどうなるんだろうと思っていた。それでも、いつも行動しながら考えています」と答えた。
関野さんのお話は、会場の参加者にも大いに刺激を与えたようだ。
商社からエンジニアへの転職活動中の30代男性は、創造性や、関野さんの「人間」に対する考え方に関心があって受講した。「一番の気づきは、ルーツを辿るということが、自分の価値観や枠組みを離れるきっかけになるんだということ。一般的には、知らないものを組み合わせて新しいものを作ると言われるが、紹介されたカレーのプロジェクトのように、じつは当たり前に接している既知のもののルーツを辿ることで、新しい視点を生み出すこともできるんだと感じた」。
また、30代のイラストレーターの男性は、ムサビの卒業生。なかでも印象的だったのは、関野さんが最後に話した、挑戦には時間が必要という視点だった。「とくに東京では、いまは本当に時間的な余裕がないと感じる。何かを成し遂げるには、短期の仕事だけでなく、中長期の視点で進める仕事が必要だとあらためて思った」。また、関野さんが、旅を続けるうえで家族との関係を犠牲にしてきたと反省的に話したことも印象的だったという。「仕事と私生活の関係はそれぞれの人が真剣に考えないといけない。その意味でも、関野さんの話が聞けて良かった」。
人類の歴史を辿る人類学の旅と、クリエイティブを学ぶ社会人向けの講座。一見、遠いように見える二つの世界だが、そのギャップのなかにこそ、じつは現代を生きる私たちにとって真に重要な視点が潜んでいるのかもしれない。関野さんの話を聞きながら、そんなことも考えた。
—
武蔵野美術大学公開講座2019 「クリエイティブを学ぶ! 〜デザイン、アートの力って?」
■第4回 2019年10月17日(木)19:00-21:00
「人類の身体と道具と社会のデザイン」を学ぶ!
講 師:関野吉晴|探検家
詳細はこちら
—